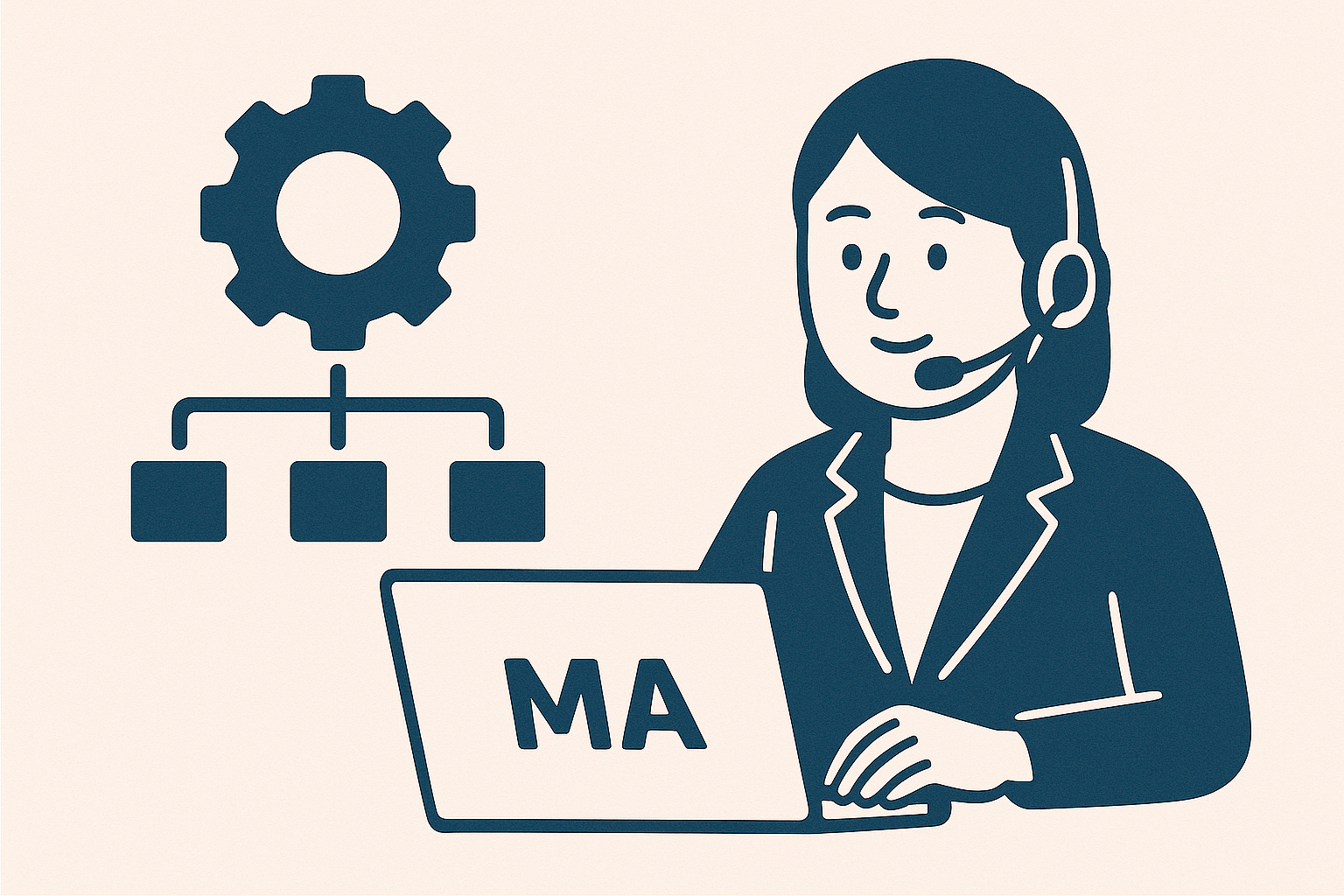営業とマーケティングが“自然に連携する”ためのナーチャリング設計──分断を乗り越える仕組みとは?

「営業とマーケ、連携できていますか?」
多くの企業で聞かれるこの問い。
マーケティングオートメーション(MA)ツールを導入し、リード獲得やナーチャリングに取り組んでいる企業ほど、営業部との連携の壁に直面しているのが現実です。
本記事では、弊社マーケティングアカデミア代表の富田がウェビナーでご紹介した内容をもとに、“自然に連携できる”営業とマーケの在り方を探っていきます。
営業とマーケがかみ合わない3つの典型的な壁
営業とマーケが噛み合わなくなる壁として、3つが頻出します。
1. SFA・CRMのデータが信用されていない
営業がSFAに入力しない、もしくは更新しないことで、マーケティングが活用できるはずのデータが「死蔵」されてしまいます。
2. ツールや施策の導入がマーケ部主導
マーケティング部が新たなMAツールやシナリオ施策を導入しても、営業現場には伝わっておらず、「現場で何も変わらない」状態になりがちです。
3. メルマガ頼みの単発施策
せっかくMAを導入しても、一斉配信のメルマガだけで終わり、営業にパスされるリードは少ないまま…。連携の“起点”すら作れていないケースも。
「連携」は設計できる──営業とマーケをつなぐ3つの鍵
まず、可視化により連携イメージを深めることが大切です。
1. スコアリングとグレーディングで“渡すべきリード”を定義
営業が動きやすい“ホットリード”の明確化が連携の第一歩です。
個人スコアの例:
- 商品ページ閲覧:20pt
- 問い合わせフォーム送信:100pt
- メールクリック:10pt
※直近行動は1.5倍で加点するとリアリティが上がります。
企業グレードの例:
- 業種が重点対象:加点
- 従業員規模や職種から購買可能性が高く・受注時の規模が大きいと推測:加点
これにより、営業部が納得感をもって対応できる“優先度つきのリード”が形成されます。
2. 営業を“通知で動かす”自動シナリオ設計
営業が「手間なくアポが増える」状態を実現するには、行動検知ベースの自動通知・トスアップが不可欠です。
シナリオ例:
|
状態 |
マーケ施策 |
営業との接点 |
|---|---|---|
|
新規CV後 |
ステップメール+スコア加算 |
トスアップ通知 |
|
サイト再訪問 |
行動検知ツールで検知 |
SlackやSFAに即時通知 |
|
更新時期 |
自動確認メール |
返答内容で営業アラート |
「いまこのお客様、動きがありました」とマーケから営業へ“そっと手渡す”自然な連携導線を設計することが重要です。
3. 営業に「成果」を見せることで、連携は文化になる
ツールやシナリオの設計よりも重要なのは、「この仕組み、アポが増えるな」「受注率が上がったな」と営業部が成果を実感できることです。
「寝ていてもアポが取れる仕組み」を目指すのです。
そのためには、
- MAの成果を営業KPIと結びつける
- 営業アラート→商談化の成功事例を社内で共有
- 1人の営業を“モデルユーザー”として設定し先に成果を出す
など、“運用”ではなく“成功体験”を提供することが、社内文化としての連携に繋がります。
まとめ:営業とマーケをつなぐのは「仕組み」ではなく「信頼」
複雑なシナリオや細かいルール設計も重要ですが、何よりも大切なのは、「営業にとって役に立つ」とマーケが信頼されること。
そのために必要なのは…
✅ ホットリードをわかりやすく届けるスコア設計
✅ “今この人”にアプローチすべき理由が伝わる通知
✅ 成果が営業KPIに直結する仕組み化
実践に向けたチェックリスト(営業企画・マーケ責任者向け)
- ホットリード定義が営業と合意できているか?
- 行動トリガーを営業通知に連携できているか?
- KPI連動で営業がMA成果を体感できているか?
- 成功事例を定期的に共有できる場があるか?
営業とマーケが対立せず、“自然に連携する文化”を根付かせる第一歩として、ぜひ今回のナーチャリングの考え方を社内でご活用ください。

マーケティングアカデミア富田
マーケティングアカデミア富田
株式会社マーケティングアカデミア 代表取締役 20代はリクルートで人材系の法人営業。飛び込みやテレアポをしたくない、でも成果は出さないと行けない、というジレンマの中、気づけばメールマーケティング・カスタマーサクセスのような動きを自然身に着けていた。狙い通り、「自分は案件や引き合いが多くてテレアポの時間が作れないし、優先すべきは今ある案件の受注」という建前を作りつつ、表彰を多数獲得。 30歳の誕生月にリクルートを卒業し、ベンチャーで教育系求人サイトの事業責任者に。はじめて経験するデジタルマーケティング・サイトやシステムの制作に苦戦しつつ、自社開発でMAツールのような機能を作りながら会員の応募を増やし事業を成長させた。 その後偶然、MAツールの運用を支援したところ、これまでの他の事業・領域よりも成果に貢献でき満足度も高かった。営業・マーケティング・システムというMAツール運用に必要な領域で全て10,000時間以上の経験を積み重ねていたことが上手く昇華された。そのため現在はMAツール運用に集中し、1社でも多く自動化施策で成果と効率を上げるための取組を行っている。